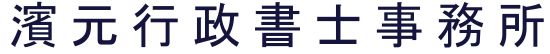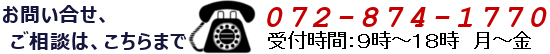株式会社を設立する際のQ&A
株式会社を設立する際Q&Aを記載しています。
当事務所が株式会社設立をする相談者から受けた際の質問も記載しています。
Q3:会社名をどう決めれば良いですか?会社名の決める際の規則はありますか?
Q4:「定款(ていかん)」とは何ですか?作ってもらえますか?
Q6:会社設立する際に、資本金はいくらにするのが良いですか?
Q1:会社設立に際して、誰が、何名必要になりますか?
株式会社を設立を希望する方との面談している時、発起人という言葉を序盤に説明します。発起人とは、「株式会社を設立しようと考えて手続きをして、資本金の出した人」と説明しています。
株式会社の登記を行い、設立が完了すれば、発起人は資本金を出していますので、株主となります。
発起人となることができるのは、人か法人(例えば株式会社など)となります。
設立手続きに際して、印鑑登録をした印鑑の押印が必要になりますので、印鑑登録をしている人、法人である必要があります。
テレビ番組で未成年の方が会社を設立したというのを見た記憶がかすかにあります。
未成年の方が会社を設立する際ですが、法定代理人である親権者の同意を得ることができれば、株式会社の発起人になることは可能です。
あと、発起人の人数は、特段の定めがないので1人でも2人でも、もっと多くの人数でも可能です。ただし、複数人の場合は、出資比率について注意が必要です。
当事務所でも、事業主1名が発起人の株式会社、個人と株式会社が発起人となった株式会社を設立した実績があります。
Q2:友人と共同で会社を設立することはできますか?
会社設立するに当たって、1人だけでなく複数人での設立することが可能なことは、上記に説明済みです。なので、友人と共同で会社を設立することも可能です。
創業に際して理念に賛同して、友達同士、以前勤めていた会社の同僚とともに会社を設立するケースが多くなってきました。
友人を会社を設立に当たって、後々の会社運営を考えて、設立前に注意することがあります。
誰が代表取締役となるのか?
役員の任期をどうするのか?
資本金の出資割合をどうするのか?
株式会社は、資本金を出す割合が多ければ多いほど、株主として権限が強くなります。
2人で会社を設立したとして、お互い同額、50%ずつで資本金を出し合ったとしたら、過半数でないことから、決めることができない場面が出てきます。
友人と共同で創業するということは素晴らしいと思います。
ただ、継続して会社を経営することを考えて、十分話し合いましょう。
Q3:会社名をどう決めれば良いですか?会社名の決める際の規則はありますか?
会社を設立するに当たって決める会社名とは、商号といいます。
商号は自由に決めることができます。
法務局に登記した商号が正式な名称となります。
個人の名称を入れたり、地域の名前を入れたりして、ターゲットとなる顧客に会社を覚えてもらいやすく伝わりやすくなるなるようにするのがおすすめです。
商号を決める上でのルール
(1)前か後ろに「株式会社」を必ず入れる
株式会社として商号の前か後に「株式会社」の文字を入れなければなりません。
当事務所では株式会社設立を希望する方に対して、「株式会社○○」の前株(まえかぶ)か「○○株式会社」の後株(うしろかぶ)どちらかになりますと説明しています。
(2)同一住所で同一商号は登記できない
同一住所で同一商号は会社の区別ができなくなるため、登記をすることはできません。
当事務所では当事務所では会社名の候補を伺った際に、法務局の登記・供託オンライン申請システムにログインして検索する、国税庁の法人番号公表サイトで検索して同じ住所に同じ社名を持つ会社が存在しないかを確認しています。
(3)特定の語句や名称は使用できません
会社の社内組織・部門を示す「支店」、「支社」、「出張所」、「事業部」などを使用はできません。
犯罪を連想する語句や猥褻な言葉も使用できません。
国や地方公共団体などの公的機関や銀行、生命保険の会社と誤認されるような名称も法律で禁止されています。
株式会社を設立するのに「合同会社○○」と会社の種類が異なる名称を使うことはできません。
(4)商号として使用できる文字が限られている
商号としてに使用できる文字には、法務局で登録可能な以下の文字に限られています。
日本文字、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐ 」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)です。
(5)他社の商標は避ける
特許庁の特許情報プラットフォームで検索することも必要です。
商号を決める際のアイデア
会社を設立する際には、商号を決める必要があります。
商号を決める際のアイデアを下記に記します。
- 個人事業で使用していた屋号に株式会社をつける
- 会社の理念や理想、目標を会社名に入れる
- 漢字だけではなくカタカナや外国語なども検討する
- 会社の理念や理想と同じ意味を持つ外国語の採用を検討する
- 外国語表示するなら読みやすいことを検討する
- ホームページを作成することから、商号のドメインが取得可能か検討する
- 会社の理念・理想から考えた造語、言葉のつなぎ合わせた造語を商号にするならカタカナ表記にすることも検討する
Q4:「定款(ていかん)」とは何ですか?作ってもらえますか?
定款とは、「会社の憲法」と言われており、会社のルールを定めたものです。会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。定款は、会社設立時に作成したものを適宜変更しながら、会社が存続している間ずっと使い続けることになります。
会社を運営していく上で、基本的なルールを定めたもので、会社を設立する際には発起人が必ず作成しなければなりません。
初めて会社を設立するという方が多いです。となると定款の作成も初めてという方は多いはずです。
ご依頼いただければ、当事務所では定款を代理で作成しております。また、電子定款を採用していますので、収入印紙4万円は不要となります。
Q5:本店所在地を決める際に注意する点は何ですか?
会社の本店が所在する場所ですが、定款に必ず記載しなければならない事項の一つであることから、会社の設立登記をするまでには決めておく必要があります。
会社の本店所在地には、制限はありません。
会社の事務所や事業を行う店舗の住所を所在地にすることとなります。
事業主の自宅住所を本店の所在地とすることもあります。
事業主の自宅として賃貸契約しているマンションやアパートなどを会社の本店所在地として考えている場合には、事前に大家さんに承認をとっておき、後日使用承諾書に署名押印してもらうとか、賃貸借契約書の使用目的と行った内容を確認しておきましょう。
賃貸物件によっては、住居専用としているために、物件オーナーが会社の事務所としての使用を認めていない場合があるためです。
登記上の本店所在地を事業主の自宅として、実際に事業をおこなっている事務所や作業所が別のケールもあり得ます。 例えば、登記上の本店所在地は事業主名義の自宅住所としているけれども、会社の事務所や作業所は賃貸契約しているテナントや倉庫でおこなっているというケースもあります。
会社設立時の本店所在地候補
- 事業主名義の自宅
- 事業主が賃貸契約しているマンション・アパート
- テナントとして貸し出している賃貸事務所
- レンタルオフィス
- バーチャルオフィス
Q6:会社設立する際に、資本金はいくらにするのが良いですか?
株式会社設立に際して資本金とは、会社を設立しようとしている発起人から払い込まれたお金のことで、創業する会社の設備投資や運転資金を含む資金になります。
会計の話をすると、払い込まれた資本金は返済義務がないお金であるといえますので、資本金の金額が大きいほど、その会社の財務上に余裕・の余力があるといえます。
では、いくらの資本金で会社を設立すれば良いでしょうか?
会社設立したいという方と面談した際、「資本金の相場って、いくらですか?」と聞かれることがあります。
資本金の額は、業種や会社の規模のより異なります。
許認可が必要な業種、例えば建設業許可の取得を考えている場合なら500万円くらいが目安だという説明をします。
何度も書きますが、資本金の額は、業種や会社の規模のより異なります。
創業に当たり、製造機械設備や車両運搬具、倉庫や工場の建物の賃貸料といった初期投資が必要なのかどうかも検討材料となります。
在庫を持つための仕入れといった運転資金を3ヶ月から半年くらいを考慮することもひつようです。
なので、創業のための設備投資額と半年分の運転資金を計算した額を合算した額を資本金として検討することから始めてはどうでしょうか。
消費税で考えると、資本金が1,000万円以上の場合は初年度から消費税の課税事業者に認定されて、消費税を納めなければなりません。資本金が1,000万円にするかどうかも、資本金の額を考える項目となります。
Q7:会社の決算月は、いつが良いですか?
決算月とは、1事業年度の最後月のことです。
で、会社の事業年度は、基本的に1年間です。個人事業を行っていれば「1月1日から12月31日までの1年間」が事業年度でした。
会社であれば、「1月1日から12月31日までの1年間」の12月決算の会社があったり、「4月1日から翌年の3月31日までの1年間」の3月決算の会社があったりと、決算月がいろいろとあります。
会社の事業年度の期間は、自由に決めることができますが、事業年度の期間を決めるポイントを下記に示します。
会社の場合、決算月の2か月後には法人税や消費税などを申告して納税しなければなりません。
会計士や税理士といった専門家に申告をお願いするにしても、伝票整理などの準備もありますので、そういった作業についても考慮する必要があります。
業界や地域での繁忙期をずらす
繁忙期と決算期が重なってしまうと、繁忙期による業務負担が増えている状態で決算業務の負担も増えることにより、業務過多になってしまいます。
業務負担が過度に増えないように、決算期と繁忙期をずらすのもひとつの考え方です。
想定される資金繰りから逆算する
上記にも説明しているように、決算月の2か月後には法人税や消費税などを申告して納税しなければなりません。
季節による売上入金が少ない時期、仕入れの支払いが多い月、従業員の賞与を支払う月などと納税時期が重ならないか、資金繰りから検討することも必要です。
消費税の免税期間と売上予想金額から検討する
会社設立時の資本金が1,000万円未満の会社であるなら、2期目までの消費税が免税されます。※2年ではなく、2期であることに注意が必要です。
そのため、会社設立の1期目を短くすると、消費税の納税が早まることがあり得ます。
会社を設立して半年経過したときの売上や給与支払額がいずれも1,000万円を超えた場合、消費税は2期目から納付することになります。
※消費税の課税義務について詳しく知りたいなら、税理士や税務署にお尋ねください。当事務所では、これ以上説明すること、お問い合わせに答えることはありません。
Q8:役員の任期は、何年が良いですか?
株式会社の取締役や監査役には必ず任期があります。
通常、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
会社が発行する全部の株式の譲渡を、会社の承認が必要とする譲渡制限事項の定めが定款に設定されている会社の場合は、最長10年まで伸長することが可能できます。
取締役や監査役の任期が到来すれば、株主総会で選任、解任の決議が行われます。
その後、株主総会の議事録作成と法務局への登記が必要となります。
法務局への登記には、登録免許税が発生します。
取締役や監査役の任期が短い場合は、任期が到来した数年おきに登記が必要となります。
取締役や監査役の任期を最長10年に伸長している場合は、10年おきとなります。
当事務所で株式会社を設立する場合は、定款に株式の譲渡には会社の承認が必要とする譲渡制限事項の定めがあることを発起人が望みます。
その場合、事業主1人の取締役のなら任期を10年で提案しています。
友人を共同して、又は、複数人で会社を設立する場合、話し合って短くすることを提案します。
※登記を専門家の司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
Q9:会社設立日はいつになりますか?
会社の設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局に会社の設立登記を申請した日です。会社の設立登記をするまでには決めておく必要があります。
法務局が休みの土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は、会社の設立日に設定できません。
会社設立の相談の面談時に、相談者から「1月1日を設立日にしたい。」という要望を伺うことがありますが、法務局が休みのため実現できませんと説明しています。
会社設立の時期が、子供の誕生日が近いこともあって、事業主さんが平日であった子供の誕生日を希望しました。
そこで、事業主の子供の誕生地となるよう司法書士事務所と進めたこともあります。
Q10:会社設立した後の手続きに何がありますか?
株式会社が設立した後、それで終わりではありません。
以下の役所への届け出が必要となります。
従業員を雇用していた場合に、届け出が必要となる場合があります。
※社会保険労務士に相談することをおすすめします。
税務署(詳細は税理士、税務署にお問合せください)
(1)法人設立届出書
(2)青色申告の承認申請書
(3)給与支払事務所等の開設届出書
(4)源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所
(1)法人設立届出書
市町村役場
(1)法人設立届出書
年金事務所
(1)健康保険・厚生年金保険新規適用届
(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(3)健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署(詳細は社会保険労務士にお問合せください)
(1)労働保険保険関係成立届
(2)労働保険概算保険料申告書
(3)就業規則(変更)届
(4)適用事業報告書
ハローワーク(詳細は社会保険労務士にお問合せください)
(1)雇用保険適用事業所設置届
(2)雇用保険被保険者資格届
金融機関(銀行、信用金庫など)
(1)法人口座を開設
近年、法人口座を開設にあたっては、金融機関の審査は厳格になっています。
創業融資をはじめとして、金融機関から融資を考えるなら、本店所在地近くで地元密着の金融機関での法人口座の開設がおすすめします。