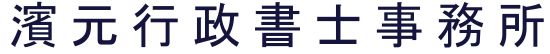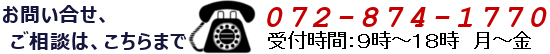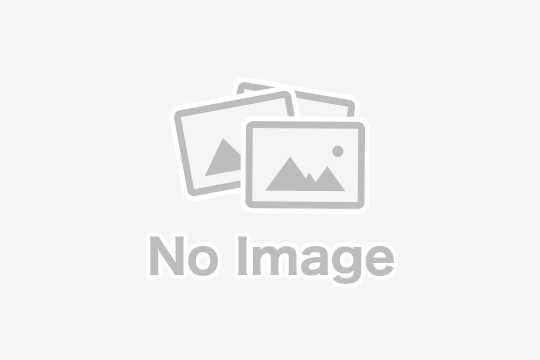2006年5月に施行された会社法により合同会社の設立が導入されました。株式会社に比べると合同会社は、比較的新しい会社形態です。
合同会社の特徴
合同会社は、出資した人を社員(株式会社の場合は株主)と呼び経営者となります。
出資した人が会社の所有者(経営者)となるため、所有と経営が一致し、出資した全ての社員に会社運営の決定権があります。
定款による組織の設計や利益配分なども自由に規定できるし、株主総会なども行わなくて良いため、意思決定のスピード感や経営の自由度が高いのが特徴的です。
会社設立で株式会社との違いを考える際、設立費用の安さをポイントの1つに挙げる相談者もいらっしゃいます。
合同会社設立に必要となる費用
合同会社を設立するのに必要な費用は以下の通りです。
| 紙の定款に貼る収入印紙代 (公証役場で支払います) |
40,000円 電子定款にする場合、4万円の収入印紙を貼る必要はありません。 |
| 登録免許税 |
60,000円 資本金の1000分の7が支払う登録免許税になります。 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
会社の実印は、登記申請時に必要となります。
加えて、銀行印、角印、ゴム印を同時に購入することをお勧めします。
はんこ屋にて会社設立セットとして販売していることが多く、2万円前後で購入可能です。
会社設立を専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
合同会社設立の具体的な手順
上記では合同会社を設立するための費用について説明してきましたが、ここからは必要となる手順について説明します。
まずは、合同会社を設立するに当たっての基本的な事柄を決めます。
発起人を決める
発起人とは、会社設立の際に定款の作成や資本金の出資といった会社設立の手続きに携わる人のことです。
発起人は1名の場合、複数名の場合があります。また、人ではなく会社が発起人の場合もあります。
なので、会社を設立しようと考える人(大概発起人になるのですが)は、自分ひとりで会社を設立するのか、複数名で会社を設立するのかにより、発起人の人数が変わってきますので考えておくことが必要になります。
商号(会社名)を決める
合同会社の商号(会社名)を決めます。
使える文字が制限されているのと、同じ住所に同じ商号がないことを除けば、基本的に自由に決めることができます。
インターネット検索すれば、同じ商号の会社の有無を確認することができます。
有名な企業と同じ名前にすると、同じ会社だと誤認することがありますので、自身の会社を守るためにも有名で実績のある会社と同じ商号とならないことも大事です。
使える文字については、法務局のホームページに記載がありますので確認してください。
「合同会社○○」や「○○合同会社」といった商号を決めていただく必要があります。
本店所在地を決める
設立する会社の本店所在地を決める必要があります。
発起人の自宅を本店にする、または、賃貸オフィスやバーチャルオフィスを本店にするなどがあります。
本店所在地は、全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。
事業目的を決めます
設立する株式会社では、どんな事業を行うのかを事業目的をして記載します。
合同会社は、事業目的実現のために設立し,運営されます。
なので、会社設立当初の事業目的に加えて、将来行う可能性のある事業を事前に書いておくことを提案しています。
また、許認可が必要な事業について、文言に注意して事業目的に記載する必要があります。
事業年度を決めます
事業年度とは、決算書を作成する際に対象となる一定期間のことをいいます。
個人事業の場合は、1月1日から12月31日が事業年度となります。
会社の場合は、自由に決めることができます。 会社を設立した際の事業年度開始日は、会社設立登記をした日となり、その日から1年以内の期間で事業年度が終了する決算日を決めます。個人事業と同じ12月31日を決算日にする方もいれば、役所の事業年度と同じ3月31日にする、4月30日、9月30日など繁忙期の状況から、決算日を決める方が多いです。
そして、決算日の翌日から次の事業年度が始まります。
なので合同会社を設立した2期目は、4月1日から翌年の3月31日だったり、1月1日から12月31日だったりします。
資本金と発起人の出資割合を決めます
資本金とは、会社を運営するにための元手資金です。合同会社設立時において、発起人が振り込みしたお金が資本金となります。この資本金が、会社設立で設備資金や運転資金といった運営に使われます。
発起人ひとりの場合は資本金の全額を出すのですが、発起人が複数の場合は均等に出すのか、出資割合を決めることになります。
合同会社では、原則、出資割合に関係なく1社員1議決権のみ持ちます。
株式会社はの場合は株式数(=出資額)に応じて利益を分配しますが、合同会社の場合は設立時の出資額が少なくとも、利益を公平に分配することができます。
合同会社の印鑑作成
上記の合同会社設立に必要となる費用にて書いているのですが、合同会社の商号が確定したのであれば、会社の印鑑を発注します。
商店街にある実店舗やインターネット上にあるハンコ屋に発注をかけます。
会社の印鑑(実印)銀行印、角印、ゴム印を同時に購入することをお勧めします。
定款を作成する
上記に記載した「合同会社設立の具体的な手順」を元にして、「定款」を作成します。
「定款」とは、「会社の憲法」と言われており、会社の基本規則を記載しています。
この「定款」には、「絶対的記載事項」という必ず記載しなければならない項目があり、その他の規定のルールがありますので、注意して作成する必要があります。
「絶対的記載事項」が書かれていない定款は、定款自体が無効となります。
そのほかに「相対的記載事項」、「任意的記載事項」等がありますので、必要項目を忘れずに記入することが必要です。
例えば、出資者の社員が死亡したときに相続人への持ち分を承継する記載が定款には必要となります。
最近では、インターネット上に合同会社の定款例を掲載しているWebサイトがありますので、参考にすればよいと考えます。それでも不明・不安であれば、専門家への相談をお勧めします。
当事務所に合同会社設立の相談があった際、相談者はインターネットに掲載されていた合同会社の定款例を基にして、私に見せてきました。必要最低限の記載があったので、特段の指摘をすることはありませんでした。
資本金の払込
登記申請に際して、資本金の払込証明書が必要となりますので、発起人個人の銀行口座に資本金の額を振り込みします。
※振り込みであり、預け入れではないことに注意が必要です。
振り込みした際に、振り込み人の名前と振込金額が通帳の明細に記載されていることが大事になります。
振り込みができましたら、(1)通帳の表紙、(2)表紙をめくった1ページ目(表紙裏)、(3)振り込み内容が記載されている明細のコピーを取ります。
(4)振込証明書を表紙としてこれらのコピーを綴ります。
登記書類の作成
「定款」認証、資本金の払込証明書を作成して、登記申請資料の作成となります。
※当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしております。
法務局に登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請します。
当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしているのですが、希望する会社設立日を事前に伺っていますので、希望日に法務局に登記申請していただいています。
その際には、会社の印鑑登録手続きも行っていただいています。
合同会社設立後の届出
法務局での登記申請が受け付けられて、しばらくすると設立登記が完了します。
そして、合同会社の登記事項証明書を手にすることができます。
合同会社が設立した後は
(1)合同会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署に届出
(2)本店所在地がある都道府県税事務所、市区町村の税務課に地方税の届出
(3)年金事務所への加入手続き
(4)労働基準監督署への加入手続き(従業員を雇った場合)
(5)ハローワークへの加入手続き(従業員を雇った場合)
(6)銀行にて法人口座の開設
といった手続きが必要となります。
以上が合同会社設立の手順になります。
濱元行政書士事務所では、これらの手続きや申請に関する具体的な手順や必要書類に
ついてアドバイスをしています。
登記申請については、提携している司法書士事務所に依頼しております。
また、会社設立後には税理士事務所と共に税務署への届け出が必要になりますし、
当事務所でも銀行口座の開設など追加の手続きを支援します。
これらの手続きも含め、弊事務所は皆様のスムーズな起業をサポートいたします。
起業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お力になれることがありましたら、誠心誠意サポートさせていただきます。
成功に向けて共に歩んでいくことを楽しみにしております。
起業支援として、下記の情報について投稿していますので、ご覧ください。